尖閣諸島は,1885年から日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い,単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って,正式に日本の領土に編入しました。
この行為は,国際法上,正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています。
同諸島は,それ以来,歴史的に一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しています。
なお,尖閣諸島は,1895年5月発効の下関条約に基づき,日本が清国から割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれません。
また,サンフランシスコ平和条約においても,尖閣諸島は,同条約第2条に基づいて日本が放棄した領土には含まれていません。
尖閣諸島は,同条約第3条に基づいて,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1971年の沖縄返還協定によって日本に施政権が返還された地域に含まれています。
【サンフランシスコ平和条約第2条】
日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い
1.
1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。
2.
この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。
その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。
3.
この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
4.また、ヴァン・フリート大使の帰国報告にも、竹島は日本の領土であり、サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていないというのが米国の結論であると記されています。
サンフランシスコ講和への道
![(チラシ)外交史料館特別展示 サンフランシスコ講和への道]()
I 外務省内における講和問題研究(PDF)
II 対米交渉準備作業(PDF)
III 吉田・ダレス会談(PDF)
IV 講和会議開催に向けて(PDF)
サンフランシスコ講和関連史料(PDF)
展示史料解説(PDF)
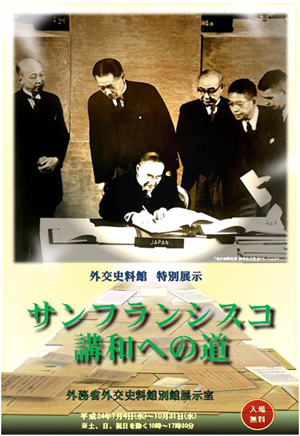
1952(昭和27)年4月28日,サンフランシスコ平和条約が発効しました。これによって連合国軍の占領が終了し,日本は独立を回復して国際社会に復帰しました。そしてその後めざましい発展を遂げたのです。しかし,講和に至る道のりは決して平坦なものではありませんでした。当時の首相兼外相であった吉田茂は,東西冷戦の難局のなか,外務事務当局を督励して対米交渉を進め,講和への道を切り開きました。今年(2012年)は,平和条約発効から,ちょうど60年になります。今回の特別展示では,講和達成に向けた日本の外交努力を関係史料によって振り返ります。この展示を通じて,日本外交が講和を実現するに至る苦闘の道程を体感していただければ幸いです。
展示概説と主な展示史料解説
(注)各テーマをクリックすると,展示の概説と主な展示史料の解説が表示されます。
I 外務省内における講和問題研究(PDF)![]()
1945年10月,外務省では来るべき平和条約の締結に備え,条約締結問題の予備的な検討を開始しました。その後,冷戦が本格化し,早期講和の実現が難しくなると,外務省は次第に東側諸国を除外した「多数講和」を講和方式とする方針を固めることとなりました。
II 対米交渉準備作業(PDF)![]()
朝鮮戦争が勃発し,1950年9月,米国が対日講和実現の意思を示したことを受け,外務省事務当局は,対米交渉に備えた対応策の検討に着手しました。また,吉田首相は有識者を集めて会合を開き,安全保障や再軍備問題等,講和に関する意見交換を行いました。これら,準備作業をもとに日本側は吉田・ダレス会談を迎えることになりました。
III 吉田・ダレス会談(PDF)![]()
1951年1月から,講和と安全保障問題について日米間で協議が行われました。吉田首相とダレス特使との会談では,自由世界の防衛に対する日本の貢献等について意見交換がなされました。また,あわせて事務レベル折衝も行われ,これら協議の結果,2月9日,平和条約と日米安全保障条約の基本的な枠組みについて合意がなされました。
IV 講和会議開催に向けて(PDF)![]()
1951年3月下旬,米国は平和条約草案を関係各国へ送付し,以後米国は英国をはじめ各国と協議を進める一方,条文をめぐって日本側との間で協議を行いました。また,平和条約案と並行して日米安全保障条約についても日米間でさらに協議が行われました。9月8日,サンフランシスコ平和条約が日本を含む49か国によって署名され,同日,日米安全保障条約(旧安保条約)も署名されました。そして,1952年4月28日,平和条約が安保条約とともに発効しました。
サンフランシスコ講和関連史料(PDF)![]()
本特別展示では,全19点の展示史料のほかに,外交史料館が所蔵する「吉田茂関係資料」や常設展示等の中から,講和関連史料を紹介します。
展示史料解説(PDF)![]()
田村清三郎著「島根県竹島の新研究」

たむら せいざぶろう
1914年に旧満州(現在の中国東北部)に生まれる。旧制松江高校、京都大法学部を経て、満州国の官僚に。第2次世界大戦後、島根県職員となり、県史編さん室主幹や県立図書館次長などを歴任。68年死去。
島根県職員だった田村清三郎氏が竹島(韓国名・独島)の領有権問題について、幅広い視点からまとめた労作。韓国が李承晩ラインを設定した2年後の1954年に著した「島根県竹島の研究」を改稿し、65年に県総務課が発行した。同年締結された日韓基本条約で、竹島問題の解決が先送りされことから、世論喚起を目指した。
内容は江戸時代から明治時代初めにかけ、竹島と呼んだ現在の鬱陵島と、松島と称された現在の竹島の歴史的沿革に始まり、現在の竹島を日本領土に編入した1905年の閣議決定を機に、名称が入れ替わった背景や、同年の島根県告示第40号の発令に至る経緯を詳しく説明。また、現在の竹島を日本側が漁業などでどう利活用してきたか、史料・文献を用いて検証した。
さらに、現在の竹島の領有権問題の変遷に触れ、自国領と譲らない韓国側に対し、その主張の疑問点や根拠のほころびを示しながら反論。「国際法の要求する先占の諸要件は完全に充足せられており、竹島の主権に関しては争う余地は全然存しない」と結び、同島が日本領土であることを強く訴えた。
本書は96年に復刻。昨年に第5刷が発刊され、ロングセラーとなるなど、功績に対する評価は、今なお高い。
内容は江戸時代から明治時代初めにかけ、竹島と呼んだ現在の鬱陵島と、松島と称された現在の竹島の歴史的沿革に始まり、現在の竹島を日本領土に編入した1905年の閣議決定を機に、名称が入れ替わった背景や、同年の島根県告示第40号の発令に至る経緯を詳しく説明。また、現在の竹島を日本側が漁業などでどう利活用してきたか、史料・文献を用いて検証した。
さらに、現在の竹島の領有権問題の変遷に触れ、自国領と譲らない韓国側に対し、その主張の疑問点や根拠のほころびを示しながら反論。「国際法の要求する先占の諸要件は完全に充足せられており、竹島の主権に関しては争う余地は全然存しない」と結び、同島が日本領土であることを強く訴えた。
本書は96年に復刻。昨年に第5刷が発刊され、ロングセラーとなるなど、功績に対する評価は、今なお高い。
